50代からやったほうがいいことも……未来の安心をつくる終活のススメ[そよ風コラムvol.3]
皆さまから多くいただく疑問の声にお答えするシリーズ、そよ風コラム。専門家の皆さまの力をお借りしながら、職員が日々学んだことを記していきます。
今回は、
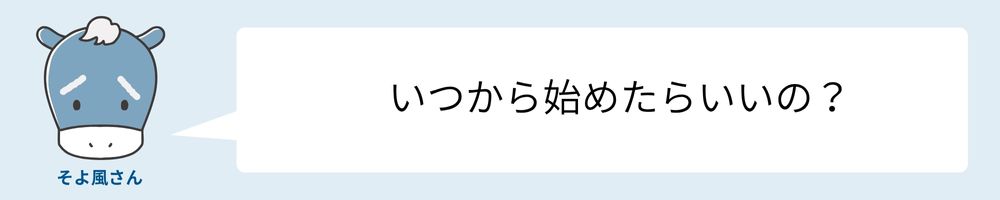
の声にお応えし、遺贈・相続の専門家である齋藤弘道先生にお話をお伺いします。
終活と聞くと「自分にはまだ関係がない」「定年を迎えたくらいから考えようかな」と感じる方も多いかもしれません。しかし終活は年齢を問わず、人生のどのタイミングからでも始められる“生活の整理”とされています。
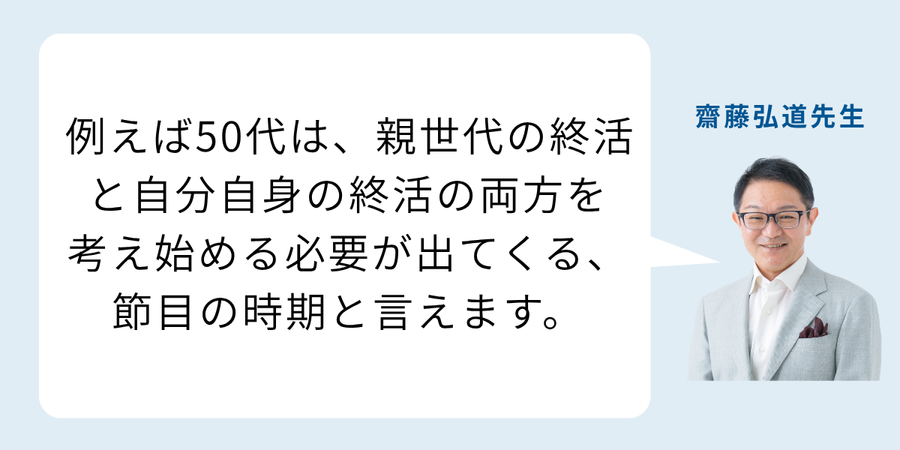
「親の終活」が急に現実になる50代
50代になると、親が70代、80代に差し掛かるケースが多いです。そんな時期に、ふとこんなことが気になり始めませんか?
- 「最近、親が物忘れしやすくなった気がする」
- 「病院への付き添いが増えてきた」
- 「もしもの時、実家の財産や相続のこと、全然話し合えていない……」
とくに注意したいのが、親の認知症リスクです。 遺言は「意思能力」があるうちにしか作成できません。認知症が進行し、判断能力が失われてしまった場合、遺言は作れなくなります。
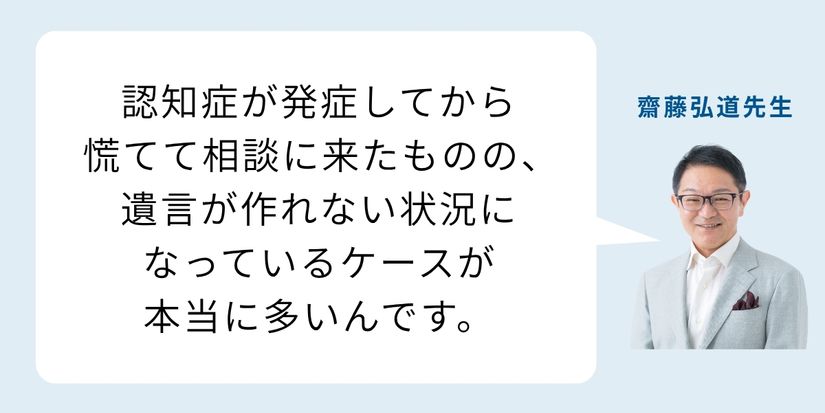
親が元気なうちに、少しずつ話を始めておくことが、後々の大きな安心につながります。
親に遺言がなかった場合、実際に起こりうるトラブルとは?
遺言がないまま親が亡くなると、家族には遺産分割協議が求められます。しかしこれが、思わぬトラブルの火種になることも少なくありません。
たとえば――
- 相続人の1人が遠方に住んでいて手続きが長期化
- 実家を兄弟の1人が引き継ぐつもりでいたが、他の相続人と意見が合わない
- 話し合いが長期化して故人の口座が凍結され、葬儀費用や医療費の支払いができない
- 相続財産の中に不動産があるため、現金化や分割で揉める
実際齋藤先生は「親の遺言がなかったことで、残された兄弟の関係が悪化した」「想像以上に手続きが煩雑で疲弊した」というケースを数多く見聞きしてきたそうです。
相続は不要な人間関係の悪化を招きかねません。だからこそ、親の元気なうちに「どの財産を誰に託したいか」を明確にし、遺言というかたちで意思を残してもらうことが、子ども世代の安心にもつながるのです。
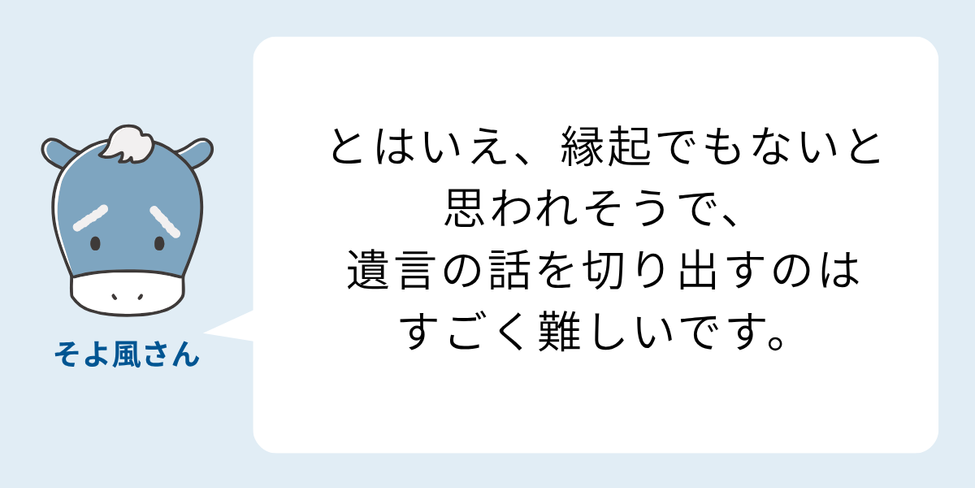
家族だからこそ、遺言の話をするのは簡単なことではありません。特に年齢を重ねるほど、こういった話に抵抗を感じる方は多いかもしれません。
次回は、どうやって家族と話す?をテーマにお届けします。
▼そよ風コラム一覧はこちら
https://www.rocinantes.org/blog/tag/bequest/
▼ロシナンテスそよ風倶楽部についてはこちら
https://www.rocinantes.org/support/donate/bequest/club/
▼そよ風倶楽部登録はこちら
https://www.rocinantes.org/support/donate/bequest/mailmagazine/
